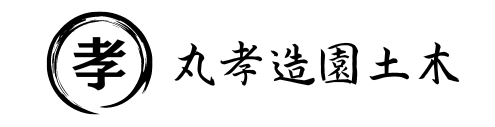【神奈川県 横浜市】造園工事・土木工事なら
営業時間
定休日:日曜・祝日
【電話受付時間】
月~金
9:30~17:00
コンクリートの基本知識
土木業界勤務以外の方からすると、コンクリートというものはさほど目立った特徴がないように思われるかもしれません。
今回はそんなコンクリートについて解説いたします。
まず、コンクリートの基本知識です。
コンクリートはどのような素材かというと
【70%】砂利や砂
【30%】セメントや水
でできている舗装材料です。
つまり、コンクリートは「砂利や砂とセメント、そして水が混ざったもの」です。
砂利や砂は「骨材」と呼ばれております。
固まる前のコンクリートは、JISの正式名称では「レディーミクストコンクリート」と呼ばれています。
そんな固まる前のコンクリートを、生コン工場(コンクリート工場)から現場に運び、その場で固めます。
現在は、コンクリート工事で製造されたコンクリートを現場に運んで固めるだけという作業ですが、かつては違いました。
現場のプラントで実際に材料を混ぜ合わせ、コンクリートを作り流し込んでいました。
昭和20年代半ばからは、コンクリート工場というものができ始め、現場では流して固めるだけという大幅な作業負担の削減が行われました。
こちらはかなり省力化に影響し、舗装工事の負担が軽減されたようです。
このように「現場で作る」から「現場では流すだけ」というような現場負担の減少が行われた理由には、輸送技術が進んできた事にあります。
トラックが移動中、荷台がくるくると回転している車両を目にされた機会は少なくないのではないかと思います。
回転しているのは、内部のコンクリートを一定の形状に固定しない事で「固まりにくくする」という意味があったのです。
また、コンクリートの運搬は時間との勝負です。
JISに認定された工場で製造されたコンクリートを使用するためには、出荷から90分以内に荷下ろしができる(コンクリートを現場に届けられる)ということが条件となります。
よってコンクリート工場はコンクリートを製造するだけでなく、出荷後のトラックの位置管理も随時コンピュータで確認しています。
品質についても保証されており、コンクリート工場はJIS認定の工事がほとんどで品質は安定しています。
どうしても各材料(砂利や砂、セメント、水)の量を、人の感覚的なところに頼り混ぜ合わせると「今日は硬め」「昨日は緩め」というように、品質にムラができてしまいます。
ですがJIS認定のコンクリート工事では自動的に機械で管理し、品質を常に一定に保っています。
コンクリートの出荷量については1990年にピークを迎え、年々減少しています。
建設工事の減少に伴い、現在では1990年の出荷量の4割と半分の量以下となっています。
次に「コンクリートの興味深い豆知識」です。
・プレストレストコンクリート
こちらは、鉄筋コンクリートをより強化したものです。
従来の鉄筋コンクリートに圧力をかけ、より強度が高まっています。
強度が高まり薄くて丈夫になることで軽量化が図れます。
・水中でも固まるコンクリート
こちらは、水中工事の際に活躍するコンクリートです。
作業現場は必ずしも全て陸上であるとは限らないため、時には水中でコンクリートを固める必要のある工事現場もあります。
その際に活躍するのが水中で固まるコンクリートです。
普通のコンクリートが水中に適さない理由として、ベストな材料比で製造されたコンクリートを水中に流し込むことで「砂利や砂、セメントか水中で水に溶け出しバラバラになってしまう」ということが挙げられます。
そこで、水中不分離性混和剤というものを混ぜ込むことで粘性が高まります。
よって水中でコンクリートがばらけにくく、固まりやすくなります。
・Co2対策コンクリート
2種類ご紹介いたします。
まず1つ目
「制作時に工場で発生したCo2をセメントに混ぜ込む」
という地球温暖化に関わるCo2対策のコンクリートです。
製造時に発生してしまう工事からのCo2をコンクリート素材に混ぜ込むことで、地球温暖化の原因のCo2を資材の一部として活用する方法です。
当初はこちらには懸念点があり、アルカリ性のコンクリートにCo2という酸性の素材が混ざることで「さび」の原因になるのではないかという懸念です。
ただ、この懸念は最新技術で「アルカリ性を保ったままCo2を混ぜ込む」という方法で安心して使用されています。
次に2つ目
「固まる時にコンクリート自体がCo2を吸収して硬化する」
というものです。
こちらは「固まる時にCo2を吸収する」というものです。
よって、上記2点の特徴のあるコンクリートを使用する場合
「制作時にCo2を吸収し、固まる時にCo2を吸収する」という
2段階においてCo2の排出を抑えることが可能な施工となります。
・ひび割れを自己修復するコンクリート
こちらは、0.2mmまでのひび割れの場合に修復することが可能なコンクリートです。
セメントの素材の中の「水酸化カルシウム」を「二酸化炭素」と反応させることで「炭酸カルシウム」を発生させます。
その炭酸カルシウムと、水とを追加反応させることでひび割れが自然と修復されるという仕組みです。
このコンクリートは、漏水を修復したり、経年連による細く発見しづらい箇所のキズを修復することができるため、長期的に安心して使用できるというメリットがあります。
このように、コンクリートにはさまざまな特徴があるものも開発されています。
今後の技術発展により、より優れたコンクリートが開発されていくのではないかと思っています。
お気軽にお問合せください
株式会社丸孝造園土木

住所
〒241-0014
神奈川県横浜市旭区市沢町703
アクセス
相鉄線鶴ヶ峰駅よりバス10分
駐車場:あり
営業時間
8:00~17:00
【電話受付時間】
月~金
9:30~17:00
※電話受付は平日のみ
定休日
日曜・祝日