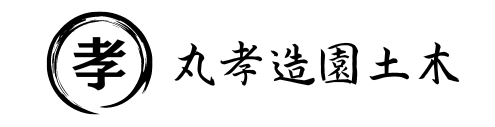【神奈川県 横浜市】造園工事・土木工事なら
営業時間
定休日:日曜・祝日
【電話受付時間】
月~金
9:30~17:00
日本の庭園・園芸の歴史
今回は「日本の庭園の歴史」について、解説していきたいと思います。
日本の庭園の歴史は、造園土木業界でお仕事をされたいかたは把握をしておいて損はない知識です。
また、造園土木だけでなく「園芸」や「ガーデニング」にご興味がある方も、知ると今よりも植物に興味を持つことが出来るようになる知識かと思いますので、是非ご参考にしてくださいね。
皆様も、国語(古文)などを勉強された際に、昔のお話には植物の美しさや季節のお花を比喩した文章が記載されていたことが記憶にあるのではないでしょうか?
事実、四季がある日本では古くから園芸が親しまれておりました。
そこで
①平安時代
②鎌倉~南北朝時代
③室町時代
④安土桃山時代
⑤江戸時代
本記事では、上記の時代の庭園についてご紹介いたします。
①平安時代の園芸
平安時代の中期では、貴族の邸宅に海や野原などの自然の風景を表現した庭園である「寝殿造庭園」が数多く作成されました。
これは海を表すようなデザインや山脈だったり、地形を庭で表すような庭園です。簡単に説明すると植物で作成したジオラマのようなイメージで頂けると近いものがあるかなと思います。
平安時代の後期では、「浄土式庭園」と呼ばれる庭園が作成されました。蓮のある池や花園、極楽浄土が表現されています。水の上に平べったい蓮の葉や、ピンクの花びらが満開になっている写真、見られたことはありませんか?
代表的な浄土式の庭園(池泉舟遊式)は下記です。
・平等院鳳凰堂
・浄瑠璃寺
・毛越寺庭園
②鎌倉~南北朝時代の園芸
鎌倉時代に入ってからは、平安時代の寝殿造の様式を受け継ぎつつ、武家時代の気強さが加わるものになりました。自然の繊細さ、美しさだけに視点を当てるのではなく、武家時代の力強さなども表現されていたようでした。
また南北朝時代から室町時代の初期にかけては、国師(高僧に皇帝より贈られた称号の1つ)の作成する西芳寺、天龍寺などが作られました。
③室町時代の園芸
室町時代になると、禅宗の思想や自然観などを反映した方式になりました。これは、直接水を用いずに石で山水の景観を表現した「枯山水」の様式が発達した。例えば、有名な庭園で砂利を川の流れに見立てて配置したり、模様をつけたりしているお庭の写真を見られたこともあるのかなと思います。
代表的な庭園には、下記があります。
・大徳寺大仙院
・龍安寺の方丈庭園
④安土桃山時代の園芸
安土桃山時代では、池や泉を鑑賞する庭園が多く作られました。豪華さや壮大さが評価されるデザインが特徴でした。自然な素朴さというよりは、豪華であることが美しいとされた時代です。
しかしこの豪華な時代でも、皆様聞いたことがあるような「わび」を本意とする茶庭(露地)も作られるようにもなりました。
この時代の代表的な庭園には、下記があります。
・醍醐寺三宝院庭園
・二条城二の丸庭園
⑤江戸時代の園芸
最後に、江戸時代の初期にはこれまでの時代の庭園技法が駆使された
・桂離宮
・仙洞御所
・修学院利休
などが作成されました。
これは①から⑤でご紹介した、これまでの庭園のスタイルを組み合わせながら作成するようになったということです。
中期になると、これまでは都中心に庭園が作成されていたものが、地方にも散見されるようになりました。これは大名が各地の城下町に作らせた「大名庭園」と呼ばれるものです。
こちらも、これまで時代の園芸技術を駆使した技法で作成した庭園です。現在でも著名な地方の大型庭園が多くあります。
代表的な庭園には、下記があります。
・岡山後楽園
・水戸偕楽園
・金沢兼六園
ここまでが平安時代から江戸時代までの、園芸の歴史です。
各時代で特徴があり、どのようなことを表現することが美しいとされていたかが分かるとても興味深い園芸の歴史の流れということが、お分かりいただけたのではないかと思います。
ちなみにですが、ここからが明治時代に入ると、園芸・造園に非常に大きな変化が訪れます。例えば、地域に公園が出来て憩いの場ができはじめたり、ドイツ幾何学式造園様式が採用された神宮ができはじめたり、ヨーロッパの様式を取り入れた折衷式のような広い芝の庭園が出来たりというような、西洋と日本の融合した庭園が見られるようになったりもしました。
このように日本の園芸の技術は時代ごとに進化、変化してきました。このような知識を持って京都旅行などに行ってみると、これまでとは違った視点で観光を楽しめるのではないでしょうか?
是非皆様も、日本の美しい庭園の歴史を実際に目で見て感じてみてくださいね。
お気軽にお問合せください
株式会社丸孝造園土木

住所
〒241-0014
神奈川県横浜市旭区市沢町703
アクセス
相鉄線鶴ヶ峰駅よりバス10分
駐車場:あり
営業時間
8:00~17:00
【電話受付時間】
月~金
9:30~17:00
※電話受付は平日のみ
定休日
日曜・祝日