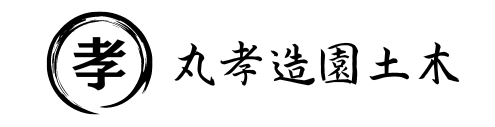【神奈川県 横浜市】造園工事・土木工事なら
営業時間
定休日:日曜・祝日
【電話受付時間】
月~金
9:30~17:00
「植物の虫害」について
虫害(虫による植物の被害)はガーデニングや園芸にご興味をお持ちの方であれば、非常に懸念されていらっしゃるのではないでしょうか?
ガーデニングや園芸を始めるか迷われている方が懸念される事項として、虫の被害についての対応ができるかどうか?ということは、虫が得意不得意であるかも含めて多く方がお悩みになっているのではないかと思います。
そこで、今回はガーデニングや園芸で突然の虫の被害でも焦ることがないように、虫害について解説させていただきます。
まず、外注による被害を形態別に分類すると、下記の4種類となります。
①食葉性害虫
②穿孔性害虫
③吸収(汁)性害虫
④虫こぶ(虫えい)形成害虫
①食葉性害虫
アゲハ、ケムシ、イモムシ、シャクトリムシ、ハムシ類、ミノムシなどの葉を食べてしまう虫です。
アメリカシロヒトリ:雑食性で、年2回(6月上旬、8月中~下旬)発生します。葉の表皮、葉脈を残して2~3週間ですべての葉を食い尽くします。
ドクガ(チャドクガ):雑食性で、若齢幼虫は群生して歯の表面を食害するため、白く透けたように見えます。成長すると分散して歯を暴食、花にも加害します。幼虫には毒針があり、注意を要します。
イラガ:年に1~2回発生し、樹木の葉を食害します。刺されると痛い毒針毛を持ちます。
コガネムシ類:成虫は目や新葉、花弁を食害し、幼虫は地中生活で値を食害し、苗木を枯らします。
②穿孔性害虫
コウモリガ、ハマキガ、カミキリムシ、キバチなど、幹や枝に穿孔する害虫の事です。
カミキリムシ:ゴマダラカミキリ、シロスジカミキリなど多種で、成虫は目を食害します。幼虫はテッポウムシとも呼ばれ、樹皮下や材部を食害し、枯死または著しい生育阻害を与えます。
③吸収(汁)性害虫
カメムシ、グンバイムシ、カイガラムシなど、幹や枝、葉で樹液を吸収するものです。
アブラムシ:植物の先端の柔らかい部分の目や花芽、新葉などに群生し、汁液を吸い成長を妨げます。念に何回も発生、雌だけで単為生殖(単性生殖)も行うので、繁殖力は強いです。すす病、ウイルス病を媒介します。
カイガラムシ:表皮から汁液を吸い、衰弱・枯死させます。大部分の種は虫体や卵が白などのろう状の被覆物で保護されています。
ハダニ:夏など、年に何回も繁殖します。葉に寄生し、汁液を吸収します。葉の色が悪く(灰白色)なり、やがて枯死して落葉します。
④虫こぶ(虫えい)形成害虫
キジラミ、アブラムシ、タマバチ、タマバエなど、葉に虫こぶを作る害虫の事を言います。
キジラミ:白粉を覆った小さな虫で群生し、吸汁する。葉の表がこぶ状に隆起します。
以上が、植物が被害を受けることの多い虫害のご紹介になります。
いかがでしょうか?ガーデニングや園芸をしていると、上記のような虫による植物の被害も多く異変に気付かれることも稀にあるのではないかと思います。その際は是非本記事をご参考いただき、対策をしていただけたらと思います。
お気軽にお問合せください
株式会社丸孝造園土木

住所
〒241-0014
神奈川県横浜市旭区市沢町703
アクセス
相鉄線鶴ヶ峰駅よりバス10分
駐車場:あり
営業時間
8:00~17:00
【電話受付時間】
月~金
9:30~17:00
※電話受付は平日のみ
定休日
日曜・祝日